こんにちは。今回は、円筒研削盤の「端面定寸装置」について、代表的な3つの測定方式をご紹介します。
加工精度を追求する上で、「端面の寸法精度」をどう確保するかは非常に重要なポイント。特に連続生産や量産加工の現場では、わずかな端面位置のずれが最終品質に大きく影響してしまいます。
そんな中で活躍するのが、「端面定寸装置」。今回はその中でも現場でよく使われている3つの方式をご紹介します。
測定装置の先端を材料に当てる「ロケーター方式」
まず最初にご紹介するのが、**「ロケーター」**と呼ばれる、非常にオーソドックスな測定方式です。
この方式では、測定装置の先端をあらかじめ材料に軽く当てて、そこから装置が信号を出した位置をNCに記録します。この信号ポイントが、端面研削の基準となります。
主な仕様と特徴:
- 加工前のポスト測定方式
- 基準となるマスターの端面位置を記憶
- 毎回、同じ取りしろ量で研削を実施
- 少し手前から測定することで、ワークとの衝突を回避
段取り時に基準となるマスター(サンプルワーク)の端面位置をNCに登録しておき、それ以降の加工では、その位置とのズレをNC上で補正します。つまり、ワークごとに端面のズレがあっても、常に一定の取りしろ量で加工できるというわけです。
エアーで起き上がる「パッシブ方式」:ポスト測定編
次にご紹介するのが、「パッシブ方式」。これは、測定装置の先端がエアーで持ち上がり、測定タイミングでエアーを切ると自然にワークに接触して測定するというユニークな方式です。
この方式には、2つの使い方があります。まずは、「加工前のポスト測定」としての使い方から。
主な仕様と特徴(ポスト測定):
- 流れてくるワークの端面位置のバラつきを測定
- 基準となるマスターとのずれを検出・補正
- ずれが大きい場合はアラーム検出も可能
ラインで連続的にワークが流れてくるような環境でも、ワークごとに端面の位置が多少ズレていても問題ありません。測定装置がそのズレ量を検出し、NCで補正してくれるので、取りしろは常に一定。安定した加工精度が保てます。
エアーで起き上がる「パッシブ方式」:インプロ測定編
同じ「パッシブ方式」でも、もう一つの使い方があります。それが、**加工中に測定を行う「インプロ測定」**としての活用です。
主な仕様と特徴(インプロ測定):
- 加工中に測定して、残り取りしろを数値で確認
- マスターの位置を基準に、加工終了点を一致させる
- ワークのばらつきがあっても、常に同じ研削結果が得られる
この方式では、加工済みのマスターを使用して、その端面位置を基準に設定します。加工中に測定装置がワークに触れた時点で「残り取りしろ」が数値で表示されるため、正確な加工終了位置が把握できます。
これにより、ワークごとに多少の寸法誤差があっても、常にマスターと同じ場所で加工が止まるため、仕上がりの精度が格段に安定します。
まとめ
| 方式 | 測定タイミング | 特徴 |
|---|---|---|
| ロケーター | 加工前ポスト測定 | 常に一定の取りしろで加工可能。シンプルで安定した方式 |
| パッシブ(ポスト) | 加工前ポスト測定 | ワークの端面位置ズレを検出・補正。アラーム検出も可能 |
| パッシブ(インプロ) | 加工中測定 | 残り取りしろを見ながら加工可能。精度と再現性に優れる |
それぞれの方式にメリットがありますので、今後の機械の選定の時の予備知識として知っていて損はないし、生産ラインの構成や加工内容に応じて、最適なものを選ぶことが重要となります。
精密加工において「端面位置の管理」は小さなことのようで、実は品質のカギを握る大きなポイントです。ぜひ、自社の生産現場でも端面定寸装置の使い方を見直してみてください!
以上、ご購読ありがとうございました!


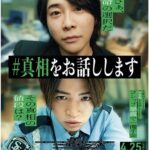
コメント